- ハンコヤドットコムTOP
- 印鑑ご利用マニュアル
- 結婚で必要な手続き
- 公的な手続き
結婚で必要な手続き
- 結婚が決まると、挙式に向けて一気に忙しくなります。しかし、
忘れてはいけない手続きもたくさん!婚姻届をはじめとする、
新生活で特に大切となる手続きをチェックしておきましょう。
婚姻届以外の公的な手続き
 結婚をしたら、婚姻届の提出だけでなく、
結婚をしたら、婚姻届の提出だけでなく、
住所や氏名の変更などを各機関に届ける必要があります。結婚にともない変更手続きが必要になる主な届出について確認しておきましょう。
転出届
新住所に変更するためには、これまで住んでいたところで転出届を出さなければなりません。
● 今まで別々の住所だった2人が結婚をして、新しい住所に住む場合
● 夫(妻)の住所地に、これから妻(夫)が一緒に住む場合
以上の場合に転出届が必要です。
| 届出先 | これまで住んでいた市区町村の役所 |
|---|---|
| 届出る人 | 本人または世帯主(代理人でも可) |
| やること | 転出届を提出して、「転出証明書」を発行してもらいます。 (引越しの2週間前から手続きできるところが多いです。 この証明書は、引っ越し先の市区町村役所に届け出る、 転入届に必要です。) |
| もちもの | ● 印鑑(認印でかまいません。本人の場合は不要です) ● 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) ● 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など) |
- 転出届と転居届の違い
- 同じ市区町村内での移動の場合は、転出届ではなく、転居届を提出します。転居届を提出する場合は、「転出証明書」は不要です。
転入届
 新しい住所の市区町村役所で婚姻届を出してから転入届を出すと、引越しと同時に2人の新しい戸籍ができます。転出・転入届の一連の流れを経て、ようやく住民票の変更手続きが完了します。
新しい住所の市区町村役所で婚姻届を出してから転入届を出すと、引越しと同時に2人の新しい戸籍ができます。転出・転入届の一連の流れを経て、ようやく住民票の変更手続きが完了します。
| 届出先 | これから住む市区町村の役所 |
|---|---|
| 届出る人 | 本人または世帯主(代理人でも可) |
| やること | 新居に住み始めた日から14日以内に必ず転入届を出します。 (転入届が終わると同時に、住民票の交付申請や印鑑登録申請もできるようになります。) |
| もちもの | ● 印鑑(認印でかまいません。本人の場合は不要) ● 転出証明書 ● 年金手帳(国民年金第1号被保険者のみ) ● 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など) ● 住民基本台帳カード(持っている場合のみ) |
印鑑登録の手続き
印鑑登録の廃止
これまで住んでいた市区町村の役所で印鑑登録をしていた場合、
転出届の手続きをした時点で自動的に印鑑登録も失効します。
また、婚姻で姓が変わり、登録している印鑑と姓が別になった場合でも、自動的に失効します。
そのため、ほとんどの市区町村では廃止の手続きは不要です。
(失効した印鑑登録証は市区町村役所で回収してもらえますが、
自分でハサミを入れて廃棄してもかまいません。)
印鑑登録の新規申請
 これから住む市区町村で印鑑登録が必要な場合、
これから住む市区町村で印鑑登録が必要な場合、
改めて新規登録をおこないます。
登録する印鑑の姓が変わらない場合や
名のみの場合は、引き続き同じ印鑑を使用できますが、
姓の異なる印鑑では登録ができないので、新しい印鑑を用意します。
| 届出先 | これから住む市区町村の役所 |
|---|---|
| 届出る人 | 本人または代理人 |
| やること | 登録を受けようとする印鑑を持参し、 役所に置いてある印鑑登録申請書に記入をおこないます。 本人確認書の提示をすると、即時に印鑑証明証を受け取ることができます。 |
| もちもの | ● 登録する印鑑(=これが実印となります) ● 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど) (代理人の場合、委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類も必要) |
パスポートの変更
 結婚して姓が変わった場合や引越しで本籍地が他の都道府県に変わった場合、有効期限のあるパスポートは変更手続きが必要です。
結婚して姓が変わった場合や引越しで本籍地が他の都道府県に変わった場合、有効期限のあるパスポートは変更手続きが必要です。
変更手続きの方法には、新規発給または訂正の2通りあります。
新規発給申請をする方法:訂正新規
新規申請と同じで、新たに作り直す方法です。
5年または10年パスポートを申請します(現在の残りの有効期限は持ち越されません)。新規申請と同額の手数料がかかり、申請から受領まで1週間程度の日数がかかります。
訂正申請をする方法:記載事項変更
今持っているパスポートを修正する方法です。
以前までは、訂正箇所をタイプ印字するだけの簡易な修正でしたが、
平成26年3月20日以降は、顔写真ページやICチップにも訂正後の内容が反映されるようになりました。
訂正後もパスポートの有効期限は変わりません。申請方法や必要書類は新規申請と同様で、受領まで1週間程度の日数がかかります。手数料はこちらの方が安価です。
| 届出先 | 住民票を登録している都道府県のパスポート窓口 |
|---|---|
| 届出る人 | 本人(代理人による申請もできるが本人の自署が必要) |
| やること | パスポート窓口へ出向き、必要書類とともに申請書を提出します。婚姻届を出した直後で、戸籍謄本ができていない場合は、婚姻届受理証明書を代わりに持参します。 後日、受け取りの際に手数料を支払います。 |
| もちもの | ● 一般旅券発給申請書(役所やパスポート窓口で入手可) ● 写真 ● 現在持っている有効なパスポート ● 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳など) ● 戸籍謄本または戸籍抄本 (婚姻後でまだ戸籍謄本ができていない人は、 婚姻届受理証明書を代用できます。) |
- ハネムーン時の注意点
- ハネムーンの際に気をつけなければならないのは、
飛行機のチケットとパスポートの氏名が一致しているかどうかです。
チケットと、パスポートの名前が違うと搭乗できません。
婚姻届提出後すぐに、新しい姓での新婚旅行を考えている方は、
パスポートの訂正または新規発給の手続きが必要になり、
どちらも受領までに日数がかかることを考慮しておきましょう。
自動車の住所・氏名変更登録
 結婚で姓や住所が変わった場合、
結婚で姓や住所が変わった場合、
車検証の記載を変更する必要があります。
この手続きを「変更登録」といい、住所・氏名の
両方が変わった場合でも、一度に変更手続きを
行うことができます。
| 届出先 | 引越し先の管轄の運輸支局 (軽自動車の場合は軽自動車検査協会) |
|---|---|
| 届出る人 | 本人(代理人でも可。ただし委任状が必要) |
| やること |
|
| もちもの |
|
運転免許証の変更手続き
 運転免許証の住所や氏名、本籍が変わったら、
運転免許証の住所や氏名、本籍が変わったら、
変更手続きを行います。
免許証は、ほかの手続きの際の本人確認としても
使用できる大切な書類です。
早めの変更手続きを行いましょう。
| 届出先 | 引越し先の所轄の警察署 |
|---|---|
| 届出る人 | 本人 |
| やること | 運転免許記載事項変更届をもらい、 必要書類とともに提出すると、その場で変更後の免許証を 受け取ることができます。 |
| もちもの | ● 運転免許証 ● 住民票の写し ● 証明写真 ● 申請用の証明写真(他の都道府県からの転入の場合、 必要になることがある) |
年金関連の手続き
 結婚した場合、年金関係の手続きは被保険者の種類によって
結婚した場合、年金関係の手続きは被保険者の種類によって
変わります。第1号になる場合は、役所へ届出を行います。
第2、第3号になる場合は、基本的に会社側が手続きを
代行してくれます。
第1号被保険者
学生、農林漁業、商工業などの自営業者とその家族
第1号被保険者とその配偶者になる場合は、氏名・住所の変更を役所に届け出ます。
新たに第1号被保険者となる人は退職日を明らかにする書類と転入届、印鑑も持参します。
失業保険を受け取っている人も第1号被保険者に該当します。
第2号被保険者
厚生年金・共済年金制度の加入者(民間会社勤務の人に適応)
結婚後も共働きする場合は、2人とも第2号被保険者となります。
それぞれが会社に、結婚届(または身上異動届)を提出すると、
必要な手続きは基本的に会社側が代行してくれます。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
結婚後に妻が会社を辞めて専業主婦になり、会社員の夫に扶養される場合など、
第2被保険者の加入資格を失った場合は、第3号被保険者(年収130万円未満の社会保険未加入者)になります。
保険料は配偶者の給料から天引きされるので、扶養される人が役所に届出をする必要はありません。
配偶者が会社に結婚届(または身上異動届)と配偶者の年金手帳を提出すれば、
必要な手続きは基本的に会社側が代行してくれます。
公的医療保険関連の手続き
 公的医療保険の主なものは3タイプです。
公的医療保険の主なものは3タイプです。
国民健康保険に加入する場合は、役所へ届出を行い
ます。健康保険・共済組合保険への加入は、
基本的に会社側が手続きを代行してくれます。
国民健康保険
自営業者、及びその家族が加入
国民健康保険加入者は、結婚で氏名・住所が変わったら、役所に届出を行います。
退職して新たに国民健康保険に加入する場合は、退職日を明らかにする書類と
印鑑も持参します。失業保険を受け取っている人も該当します。
健康保険
民間会社勤務の人、及びその家族(被扶養者)が加入
結婚後もお互いに働き続ける場合は、結婚届(または身上異動届)をそれぞれの
会社に提出しましょう。
また、この保険に加入している配偶者に扶養される人(年収130万円未満の社会保険未加入者)は、配偶者の会社の保険に加入することになり、
保険料は配偶者の給料から天引きされます。
配偶者が会社に結婚届(または身上異動届)と配偶者の年金手帳を提出すれば、
必要な手続きは基本的に会社側が代行してくれます。
手続き後すぐに保険証が配偶者の会社から支給されます。
共済組合保険
公務員、及びその家族(被扶養者)が加入
同上。
【まとめ】公的な手続きに必要な印鑑
| 必要な届出・手続き | 必要な印鑑 | |
|---|---|---|
| 婚姻届 | 婚姻届(※旧姓の印鑑が必要) | 認印 |
| その他 役所での届出 |
転出届 | 認印 |
| 転入届 | 認印 | |
| 印鑑登録 | 実印 | |
| 国民健康保険の手続き(必要に応じて) | 認印 | |
| 国民年金の手続き(必要に応じて) | 認印 | |
| 氏名・住所 変更手続き |
自動車変更登録 | 認印 |
- 印鑑の種類について
-
- 実印
- 住民登録をしている市区町村に印鑑を登録し、
実印が必要なときに、印鑑証明を受け取れるように
しておくハンコのことです。
- 認印
- 登録していない印鑑すべてを指して、認印と呼びます。
使用頻度が高く、自身のサインのように扱われます。
(シャチハタやスタンプなどは印面がゴム性で変形しやすく、また同じ印面が量産されている可能性もあるので、公式な文書にはふさわしくありません。)
おすすめの個人印鑑特集
その他のおすすめ特集
届出先により規定や方法が異なる場合もございますので、あくまで一般的な例としてご参考ください。
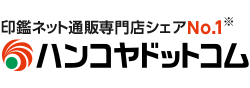


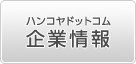
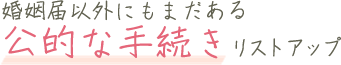





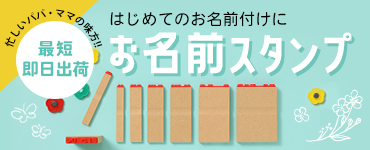

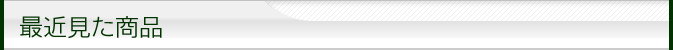
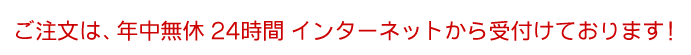
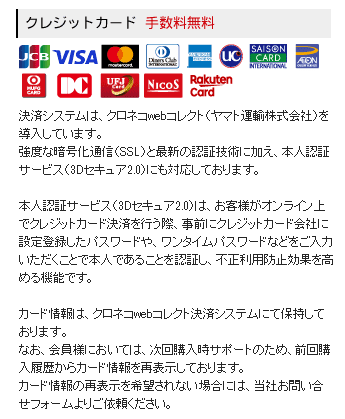
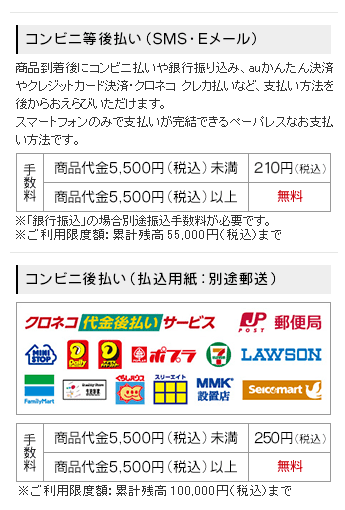
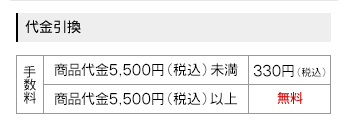
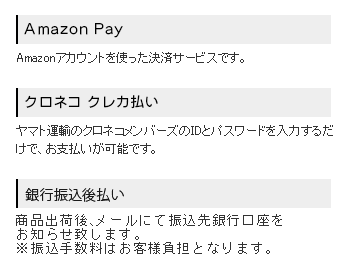
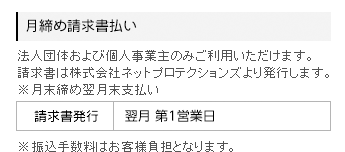
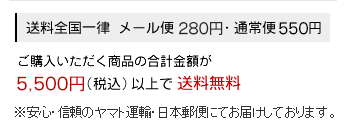
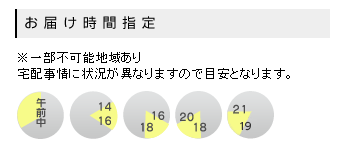
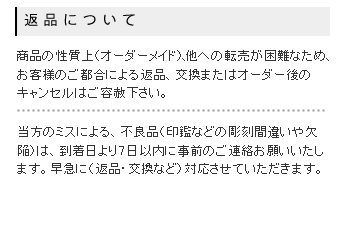




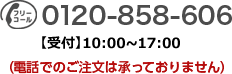

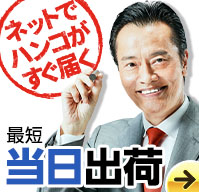



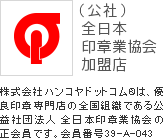



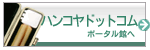 印鑑・はんこの総合サイト
印鑑・はんこの総合サイト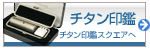 チタン印鑑サイト
チタン印鑑サイト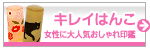 おしゃれ印鑑のキレイ はんこ
おしゃれ印鑑のキレイ はんこ 伝統と匠の技が作る印鑑
伝統と匠の技が作る印鑑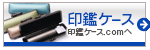 印鑑ケース専門店
印鑑ケース専門店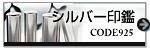 シルバー 印鑑 CODE925
シルバー 印鑑 CODE925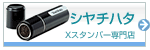 シャチハタ ネーム印
シャチハタ ネーム印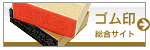 ゴム印/オリジナルスタンプ
ゴム印/オリジナルスタンプ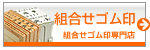 組み合わせゴム印・住所印
組み合わせゴム印・住所印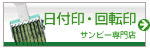 データ 印・ ハンコ
データ 印・ ハンコ お名前スタンプ
お名前スタンプ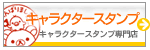
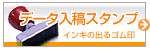 はんこやどっとこむスタンパー
はんこやどっとこむスタンパー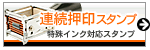 特殊インク 対応 スタンプ
特殊インク 対応 スタンプ 印刷総合
印刷総合 名刺
名刺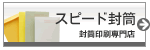 スピード封筒
スピード封筒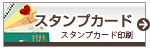 スタンプカード 印刷専門店
スタンプカード 印刷専門店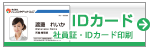 社員証/IDカード 専門店
社員証/IDカード 専門店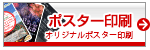 オリジナル ポスター印刷
オリジナル ポスター印刷 オリジナルパンフレット印刷
オリジナルパンフレット印刷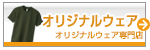 オリジナルTシャツの作成
オリジナルTシャツの作成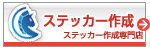 シール/ステッカー 印刷
シール/ステッカー 印刷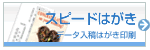 スピードはがき
スピードはがき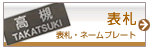 表札館
表札館 郵便ポスト
郵便ポスト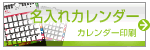 名入れカレンダー専門店
名入れカレンダー専門店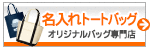 オリジナルトートバッグ
オリジナルトートバッグ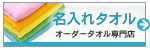 粗品タオル
粗品タオル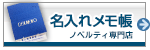 名入れメモ帳
名入れメモ帳 クリアファイル 印刷専門店
クリアファイル 印刷専門店 のぼり旗 専門店
のぼり旗 専門店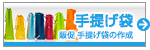 オリジナル 手提げ袋の製作
オリジナル 手提げ袋の製作

