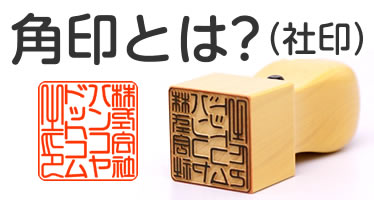朱肉とは?種類やスタンプ台との違い、朱肉の選び方を解説
- 公開日:
- 更新日:
書類に印鑑・はんこの捺印を求められた際は、朱肉を使って押すのが前提です。
しかし、朱肉についてよく知らないという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、朱肉とはどのようなもので、どういった用途・種類があるのかについて解説しています。
また、朱肉とスタンプ台との違いや朱肉の選び方、朱肉の補充方法、朱肉が乾燥したときの復活方法なども詳しくまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。

朱肉(しゅにく)とは
朱肉とは、印鑑・はんこの印面にインクを付けるときに使用する印章用品です。
容器の中の印肉(スポンジや植物繊維に朱色の顔料を染み込ませたもの)に、印鑑・はんこの印面を押し当ててインクを付着させます。
一般的には、印肉と印肉を入れる容器の2つを合わせて「朱肉」と呼びます。
印鑑・はんこに朱肉を使う理由
印鑑・はんこに朱肉を使う理由は、印影(紙に残る朱肉の跡)の長期保存に適しているためです。
朱肉に含まれる油性顔料は、耐光性(光による劣化・変色への耐性)や耐水性に優れ、環境の影響を受けにくい特性があります。
年月を経ても印影の状態を維持できるため、印鑑・はんこでの捺印が求められる書類は、朱肉を使うことを前提としています。
印鑑・はんこに朱肉を付けるときは、印肉を軽く2~3回叩くだけでOKです。
力を入れて何回も叩くと、印面の溝に朱肉が入り込んでしまい、きれいな印影には仕上がりません。
また、溝に朱肉が残ると印面の劣化につながる恐れがあるため注意しましょう。
【合わせて読みたい】
印鑑のキレイな(捺印)押し方|みんなの知らないはんこの話
朱肉の種類
朱肉には大きく分けて、「スポンジ朱肉」と「練り朱肉」の2種類があります。
この段落では、スポンジ朱肉・練り朱肉それぞれの特徴について解説いたします。
スポンジ朱肉

スポンジ朱肉は、優れた速乾性を持つスポンジタイプの朱肉です。
ひまし油、合成樹脂、顔料(色素)などを原料とした「朱油(しゅあぶら)」というインクを、フエルトやスポンジに染み込ませて作られます。
家庭やオフィス、役所などさまざまな場所で使用されているポピュラーな朱肉で、現在朱肉と言えばスポンジ朱肉を指します。
- 【スポンジ朱肉のメリット】
- スポンジ朱肉のメリットは、印影の乾きが早いことです。
捺印して数秒で乾く速乾タイプの商品もあり、大量の書類に捺印が必要なシーンで重宝されます。
また、インク補充などのメンテナンスが簡単、携帯用から法人印鑑向けの大きいサイズまで展開されていることもメリットにあげられます。
- 【スポンジ朱肉のデメリット】
- スポンジ朱肉のデメリットは、練り朱肉と比べて印影の鮮明さや色の深みが少ないことです。
また、時間とともに印影が色褪せることもあるため、長期保存が必要な書類にはやや不向きです。
練り朱肉

練り朱肉は、スポンジ朱肉が登場するまで主流だった歴史のある朱肉です。
よもぎや和紙などの植物繊維に、銀朱(ぎんしゅ)、ひまし油、白蝋(はくろう)、松根油(しょうこんゆ)、顔料(色素)などを練り混ぜて作られるため、インクよりも粘りがあるのが特徴です。
印影は鮮明で長期保存にも長けているため、重要な書類や書道・絵画などの芸術作品への捺印に向いています。
なお、練り朱肉の中には、より濃厚な質感の「印泥(いんでい) ※1」という朱肉もあります。 印泥は粘りが強く、扱いにコツがいりますが、色濃く美しい印影を長期間残せるため、書道や絵画に押す落款印(らっかんいん) ※2におすすめです。
- 【練り朱肉のメリット】
- 練り朱肉のメリットは、印影の仕上がりが美しく、年月が経過しても鮮明な印影を維持できることです。
加えて、容器には漆器や金属、陶磁器などが使われているため、全体的に高級感があります。
練り朱肉は、定期的にメンテナンスをすれば一生モノのため、長い目で見るとコストパフォーマンスに優れた朱肉と言えます。
- 【練り朱肉のデメリット】
- 練り朱肉のデメリットは、印影が乾くまでに時間を要することです。
また、定期的にメンテナンスを行わないと油分が不足したり、カビが生えたりすることもあるため、丁寧な扱いが求められます。

※1 印泥(いんでい)は、主に中国で生産されている練り朱肉です。
中国で産出される辰砂(しんしゃ)という鉱物を主原料に、よもぎを乾燥させた「もぐさ」と、職人が秘伝として継承している油を練り混ぜて作られます。
※2 落款印(らっかんいん)とは、落成款識印(らくせいかんしいん)の略語で、書道や絵画などの作品が完成したことを示すために作者が押す印のことです。
印鑑ケース内蔵の朱肉はあくまで緊急用
印鑑ケースの中には、ケースの内部に小さい朱肉が内蔵されているタイプもあります。
見た目は小さいスポンジ朱肉のため、通常の朱肉を使わずに印鑑ケースの朱肉で捺印している方も多いでしょう。
しかし、印鑑・はんこが求められる書類には、通常の朱肉での捺印が望ましいです。
印鑑ケースの朱肉は、通常の朱肉と比べてスポンジの目が粗くインクも付きにくいため、印影に縞(しま)模様が表れることがあります。
使ってはいけないものではありませんが、印鑑ケースの朱肉はあくまで、通常の朱肉がないときの緊急用としての使用がおすすめです。
朱肉とスタンプ台の違い
朱肉は印鑑、スタンプ台はゴム印に使用するもの
朱肉とスタンプ台はインクの性質が異なり、朱肉は油性顔料のみ、スタンプ台は主に水性顔料系インクです。
そのため、朱肉は「印鑑」、スタンプ台は「ゴム印」に使用するものとして作られています。
油に弱い性質を持つゴム印を朱肉に使用した場合は、ゴム面が変形したり溶けたりする恐れがあります。
反対に水性系のスタンプ台を印鑑に使用すると、印材によっては印面に色素が染み込んで変色する恐れがあります。
そのまま使用を続けると、印面の劣化にもつながるため注意しましょう。
朱肉とスタンプ台の使い分け方
朱肉は、耐光性(光による劣化・変色への耐性)や、耐水性に優れた油性顔料が含まれることから、印影の長期保存に適しています。
そのため、契約書や誓約書などの法律で保管期間が定められている書類には、朱肉で捺印するのが決まりです。
スタンプ台は水性系インクが主流で、ゴム印で押印してもよい書類(社内書類や封筒・ハガキなど)への使用を前提としています。
契約書等の書類にスタンプ台で捺印した場合、印影の変色・退色によって法的効力が失われる恐れがあるため注意しましょう。
朱肉には印鑑、スタンプ台にはゴム印と、性質に応じて正しく使い分けることが大切です。
【朱肉とスタンプ台の使い分け方】
| 朱肉 | スタンプ台 | |
|---|---|---|
| 見た目 |  |
 |
| 用途 | 印鑑に使用する | ゴム印に使用する |
| 使える書類の例 |
契約書 誓約書 入社書類など |
社内書類 領収証 回覧 その他(封筒・ハガキなど) |
朱肉と間違えてスタンプ台で捺印したときの対処方法
スタンプ台で押した印影は長期保存に適しておらず、保存環境によっては印影が色褪せて薄くなることがあります。
印影が薄くなると書類の法的効力が失われる恐れがあるため、朱肉と間違えてスタンプ台で捺印した場合は対処する必要があります。
最も適切な方法は書類の作り直しですが、状況によっては難しい場合もあるでしょう。
その場合は、間違えて押した印影にボールペンで打ち消し用の二重線を引き、その横に朱肉を付けた印鑑で押し直します。
このとき印影が重なってしまわないよう、間違えた印影から少しスペースを空けて押すとよいです。
朱肉の選び方
いわゆる普通の朱肉が欲しい場合は【スポンジ朱肉】

家庭やオフィスに置いてある、いわゆる普通の朱肉が欲しい方には、スポンジ朱肉がおすすめです。
速乾タイプや携帯に便利なコンパクトサイズ、法人印鑑向けの大きいサイズなど種類が豊富なため、シーンに合わせて朱肉を選べます。
「すぐに使えて、すぐに乾く朱肉が欲しい」という方は、日常での使用に特化したスポンジ朱肉を選ぶとよいでしょう。
- 【スポンジ朱肉は、このような方におすすめです】
-
- 手軽に扱える朱肉が欲しい方
- 早く乾くタイプの朱肉が欲しい方
- 印鑑と朱肉を携帯する機会が多い方
重要な書類・作品に捺印したい場合は【練り朱肉】

重要な書類や、書道・絵画などの作品に美しい印影を残したい方には、練り朱肉がおすすめです。
練り朱肉で押した印影は、鮮やかで深い色合いため、書類や作品の見栄えを良くします。
また、長期保存にも適しているため、法律で保存期間が定められている書類には、練り朱肉で捺印しておくと安心です。
練り朱肉は見た目も高級感があり、定期的にメンテナンスをすれば一生モノのため、就職祝いや結婚祝いなどのプレゼントにもおすすめです。
- 【練り朱肉は、このような方におすすめです】
-
- 書道・絵画などの作品に美しい印影を残したい方
- 保存期間の定めがある書類に捺印が必要な方
- お祝いで朱肉をプレゼントしたい方
朱肉の補充方法
朱肉を使い続けていくうちに、印影がかすれたり欠けたりすることがあります。
そのようなときは、朱肉にインクを補充してみましょう。
スポンジ朱肉の場合は朱肉用のインクを補充し、練り朱肉の場合は補充用の練り朱肉を補充します。
- スポンジ朱肉
- 朱肉用補充インク
- ティッシュペーパー
- 新聞紙(あると便利)
- 【スポンジ朱肉のインク補充手順】
- 朱肉は、メーカーや商品によって補充インクの種類が異なります。
まずは、お手持ちの朱肉のメーカーや商品名を確認しましょう。
スポンジ朱肉の場合は、ふたや底面に記載されていることが多いです。
メーカーや商品名を確認したら、お手持ちの朱肉専用の補充インクを購入しましょう。
-

- キャップをつけたまま、朱肉用補充インクをしっかりと振ります。
- 朱肉用補充インクのキャップを外し、ノズルを朱肉の盤面に軽く押し当てます。
- ゆっくりと円を描き、均一に浸透するよう少しずつ塗りこんでいきます。
- インクが完全に浸透するまで放置します。
- 朱肉の表面にティッシュを軽く押し当てて、余分なインクを拭き取ります。
- 朱肉用補充インクのキャップを閉めて補充完了です。
※上記画像の朱肉は、シャチハタの商品です
朱肉が乾燥したときの復活方法
朱肉は定期的にお手入れすれば、長く使い続けることができます。
そのため、朱肉が乾燥したときは正しい方法でメンテナンスを行いましょう。
スポンジ朱肉が乾燥した場合は、盤面のスポンジに朱肉用インクを補充すれば復活します。
練り朱肉は乾燥すると固まる性質のため、ヘラを使って表面を練りほぐしましょう。
【練り朱肉が乾燥して固まったときの練りほぐし手順】
-

- まずは表面を触って、感触を確かめましょう。
全体的に固まっている場合は、温めて練りほぐしができるようにします。
容器から取り出せる場合は、取り出した中身のみをラップに包み、電子レンジで様子を見ながら少しずつ温めます。
取り出せない場合は、容器の底に離れた位置からドライヤーの温風をあてる、または耐熱ポリ袋に入れて湯せんで温めるなどの方法を行いましょう。 ※朱肉を温める際は、やけどに注意してください。
- まずは表面を触って、感触を確かめましょう。
-

- 温めて柔らかくなったらヘラを差し込み、油分と顔料を混ぜあわせます。
-

- 固まっている部分と柔らかい部分が均一になるように練ります。
柔らかい部分を押し上げる形で練り直すときれいに仕上がります。
- 固まっている部分と柔らかい部分が均一になるように練ります。
-

- 捺印時にムラが出来ないように、表面を整えれば完成です。
※朱肉が乾燥したときにやってはいけないこと
朱肉の成分には油が含まれているため、水分は禁物です。
水やお湯を足すと、油分が分離して使用できなくなることがあるので注意しましょう。
朱肉のネット通販なら、ハンコヤドットコムがおすすめ
朱肉をネット通販で購入するなら、印鑑通販専門店のハンコヤドットコムがおすすめです。
速乾タイプの朱肉や携帯に便利なコンパクトタイプの朱肉のほか、高品質な練り朱肉や朱肉用補充インクなどのサプライもご用意しています。
また、最短即日出荷に対応していますので、お急ぎで朱肉が必要な場合も安心です。